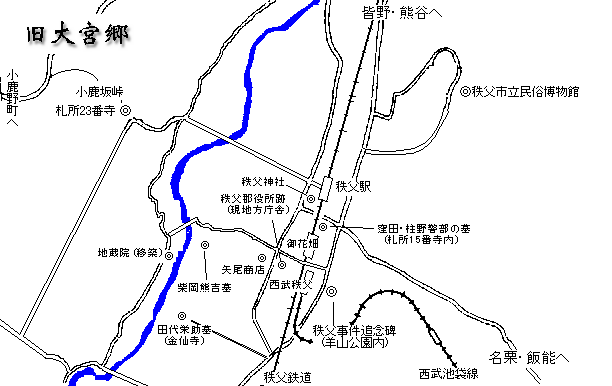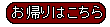|
大宮郷
大宮郷は、絹の大市をはじめとする秩父郡の経済活動の中心でも、妙見宮の大祭(現在の秩父夜祭り)が行われる秩父郡の精神的中心地でもあった。
札所23番音楽寺
秩父困民党は、1884(明治17)年11月2日の午後には、小鹿坂峠の下、郡都大宮郷を眼下に見下ろす秩父札所23番音楽寺に集結した。
彼らは、大宮郷から国家権力が逃亡し去ったことを確認すると、同寺の梵鐘を乱打し、それを合図に河岸段丘を駆け下り、武ノ鼻の渡し場付近の荒川を押し渡り、郷内に突入した。
秩父困民党無名戦士の墓
音楽寺周辺で、困民党の戦闘は行なわれていないから、ここで亡くなった人もいない。したがって、その名に反してこの碑は、墓碑ではない。
また、碑文には「われら秩父困民党 暴徒と呼ばれ 暴動と呼ばれることを拒否しない」とある。
秩父事件参加者や遺族にとって、「暴徒」とは差別的呼称と受け止められてきた。
復権のための運動は、「暴徒史観」とのたたかいであった。この碑にあるように、差別的呼称を肯定する見方は、適切でない。
また、副碑の碑文は、秩父事件の政治的背景を全く説明していない。秩父事件がこれだけの規模と思想性を持ち得た本質にふれないままでは、秩父事件の意義は理解できないだろう。
地蔵院
大宮郷突入後、田代栄助は、井出為吉・小柏常次郎・井上伝蔵らと、同郷近戸町の地蔵院に入り、仮本陣とした。
ここで、大宮郷の高利貸井上四郎次が建物の中に隠れているのが発見された。
事件後地蔵院は、地元の信仰の場、また秩父事件を体験した歴史的建造物として近戸の地にあり続けたが、1982(昭和57)年、消防器具置き場建築に伴い、撤去されることになった。
建物は、秩父市在住の中島弥助氏によって、近戸にほど近い別所地区に移築された。今となっては、秩父事件の歴史を語る、貴重な建造物だ。
柴岡熊吉の墓
熊吉は、大宮郷近戸町出身で、秩父困民軍会計長兼大宮郷小隊長。
荒川村上田野の千手観音堂の天井には、近戸川熊吉の名で奉納された相撲絵が掲げられている。
裁判では軽懲役8年の判決を受け、翌年10月に獄死。戒名は好道義忠居士。
秩父事件追念碑
羊山公園の一角には、尾崎咢堂の揮毫による秩父事件追念碑がある。
これは、困民党発起人の一人、落合寅市の子息である落合九二緒氏(故人)によって、1965(昭和40)年に建立されたものである。
秩父市立民俗博物館
市内を見下ろす高台の一角にある。
事件の年に建築された大宮学校の建物である。
高利貸刀屋の大黒柱や「革命本部」の領収証など、秩父事件関係の展示や、農具、生活用具など幅広い展示がある。
郡役所あと
郡役所あとは現在、埼玉県秩父地方庁舎になっている。
建物は今と違い、西(矢尾百貨店の方)を向いていたらしい。
なお、このとなりのNTT秩父の場所が当時の大宮郷警察署、矢尾商店や大宮郷裁判所は現在地に存在した。
矢尾商店
矢尾百貨店には、事件当日の市内のようすや、柴岡熊吉ら困民軍幹部とのやりとりなど、興味深い事実を満載した「秩父暴動事件概略」という記録が残されている。
秩父神社
秩父神社は当時より規模こそ小さくなったが、重厚な森に囲まれた、由緒ある神社である。
観光面で著名な「秩父夜祭り」や「川瀬祭り」はこの神社の祭礼である。ここを訪ねたら、となりの「秩父まつり会館」を合わせて見学するとよい。
札所15番少林寺
札所15番寺には、秩父事件で殉職した警官2名(窪田鷹男・青木与市)の墓がある。
田代栄助の墓
困民党総理。
山繭飼育を手がける精農であるが、地域の弱者に人望が厚かった。事件後死刑。
辞世は、「振り返り見れば昨日の影もなし 行く末暗し死出の山道」
|