
泥棒に会う山旅。
中里介山の『大菩薩峠』(全41巻)に、七兵衛という心やさしい泥棒が登場する。
七兵衛は甲州街道・青梅の裏宿出身とされるのだが、実在の人物。
七兵衛氏の墓(首塚)を見るためだけにわざわざ出かけるのはどうもなぁ・・と思っていたのだが、青梅丘陵ハイキングコースをしばし歩き、七兵衛屋敷あと(現在七兵衛公園)と首塚(宗建寺)を見学すれば、ちょうど一日コースになる。
ちなみに、鼠小僧次郎吉氏は秩父出身で、彼の屋敷あとは城峯山登山口近くにある。

泥棒に会う山旅。
中里介山の『大菩薩峠』(全41巻)に、七兵衛という心やさしい泥棒が登場する。
七兵衛は甲州街道・青梅の裏宿出身とされるのだが、実在の人物。
七兵衛氏の墓(首塚)を見るためだけにわざわざ出かけるのはどうもなぁ・・と思っていたのだが、青梅丘陵ハイキングコースをしばし歩き、七兵衛屋敷あと(現在七兵衛公園)と首塚(宗建寺)を見学すれば、ちょうど一日コースになる。
ちなみに、鼠小僧次郎吉氏は秩父出身で、彼の屋敷あとは城峯山登山口近くにある。
読書ナンバー1114。斎藤幸平『人新世の資本論』(集英社新書)。
マルクスの読み直しによって現代の現代の課題にどう取り組むかを提起している。
ちょっとびっくりするようなマルクスの読み方だ。
著者はいきなり、人類の経済活動を原因とする気象変動によって、地球環境を修復不可能な状態に至った現在、局面を打開するのはマルクスの考え方にあるという。
マルクス主義とは、ソ連や中国で実験され、すでに破綻した古くさい理論だと考えるのが普通だと思う。
初期マルクスのセンシティブでラディカルな見解は魅力的だが、著者は、晩期マルクスに注目される。
晩期マルクスは、生産力の発展が社会発展の原動力だという進歩史観に懐疑的で、共同体に基礎をおくコミュニティ的な社会を構想していたが、思想的にそれは完成されなかったと著者は言われる。
これは、一般的な史的唯物論の理解とは相反する理解である。
マルクスをていねいに読んだことなどないので、この見解の当否について判断する資格はないのだが、もしそうであれば、世界が当面するもっとも深刻な危機を解決する方向性をマルクス主義が示していることになる。
理論レベルで正しくても現実性はないのではないかという向きもあるかもしれない。
マルクスが夢想したコミュニティ社会は、価値(マルクス主義の教科書でいう交換価値)ではなく、使用価値を価値とする経済関係を基礎とする。
物々交換は、商品経済登場以前の原始的な経済関係だと思われているが、じつは使用価値同士の交換であり、資本主義経済を乗り越えるもっともエコな経済のあり方なのである。
自分のサイトにノートした本が1000冊を超えた。
じつは、読んだことを忘却してしまい、ノートを2回書いた本もあるのだが、分冊本も1点として数えているので、1000冊は超えていると思う。
ノートをホームページに載せ始めたのは1996年4月だから25年かかったことになる。
もっと以前からこのようなものを作ればよかったが、HTMLを習得したのが25年前だったので、やむを得ない。
これからもぼちぼち書いていきたい。

午前中、集落の新年会。
中里介山の『大菩薩峠』を読んだ。
よく知った地名がたくさん出てくるので、親しみ深かった。
読書ノートにも書いたが、小説としてはともかく、幕末の空気感を感じさせる作品だと思った。
写真は、表尾根から見た相模湾。

読書ノートに『博多・沖縄への旅』を追加。
以下は、該ノートと同文である。
著者による博多・沖縄紀行。
「日本」の大陸への玄関口だった博多という町のことも知りたいが、何度か出かけたことのある沖縄の方により興味をそそられる。
歴史学あるいは人類学あるいは民俗学といった諸学によってクールにアプローチするのもよいが、実績ある作家である著者だから許されるいくらかウェットなアプローチもよいと思う。
人類学の中には、琉球人とアイヌ人の共通性を指摘する意見がある。
それが的を射ているとすれば、彼らこそが原「日本」人であり、遅れて大陸からやってきて、列島中心部に跋扈したインベーダー支配者(それが「日本」の支配階級となる)によって南北の「辺地」へ追いやられたという展望も成り立つ。南北の原「日本」人たちには、動物や鳥や植物や風や雪など、あらゆる自然のことどもの中に神を見出し、神を恐れ、神とよく折り合いをつけつつ日々の暮らしを築くという、共通した生き方がある。
神に仮託しつつ語られるこれらの知恵は、その後も、列島民の意識の基層をなしてきた。一方インベーダーの一般民たちは、先住民に学びながら、造山活動によって作られた急峻なこの列島で暮らす知恵を編み出していった。
何も学ばなかったのはインベーダーの支配者たちだった。彼らは自分たちの暖衣飽食生活の永続のみを願い、権力を行使してきた。
まさに嗤うべきことだが、彼らインベーダー支配者の、陰険で残忍な策動の羅列がいわゆる「日本史」であり、インベーダー支配者のおこぼれにありつくことによっていい思いをしてきた者たちによってでっち上げられたのが、「日本の伝統」である。沖縄で感じた、心が洗われるような思いを著者は、「情」と表現している。
適切な表現だと思う。神=自然を畏敬し感謝し、神=自然とともに自分たちの暮らしを紡ぐ沖縄の心を、インベーダーの中でもひどく低劣な心性の持ち主である現在の為政者たちが理解できないのは、当然である。
相変わらず、オカノリを重宝している。

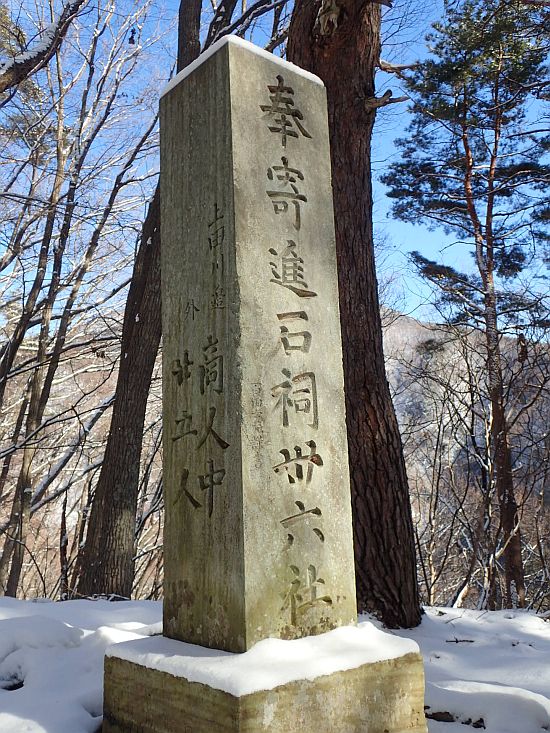

『週刊金曜日』で、佐高信氏が、尾崎放哉の「咳をしても一人」という句にふれていた。
暮れの12月20日に三ツドッケに登った際、かなり厚着をして、枯れていた一杯水から下って水を取りに行った。
下り15分、登り25分程度だったが、ここで大汗をかいてしまい、その後冷えて風邪ひきになった。
風邪を引いても熱も出ないことが多い。
今回も、激忙の最中だったこともあって自然に治癒したのだが、それ以来咳がとまらなくなった。
似たような咳で、百日咳とかマイコプラズマ肺炎などの診断をいただいたこともあった。
今回は医師に診てもらってないのだが、たぶん咳喘息だと思う。
そんな状態だったので、「咳をしても一人」がいたく気になったのだった。
吉村昭氏の放哉伝『海も暮れきる』を読んだ記憶があるのだが、本は見あたらないし、1996年以来書いている読書ノートにも記録がない。
おそらくもっと以前に読んだのだろう。
しかたがないから、また手に入れた。
写真は、太郎山の風景。

ロキソニンの服用をやめたので、傷の治癒速度が遅くなったような気がするが、明らかに気のせいである。
術後一週間でここまで回復できるとは驚きだし、医療現場には感謝にたえない。
古琉球や平泉政権をみていると、中世「国家」を近代国家の概念で腑分けすることにあまり意味がないことに気づかされる。
例えば古琉球は、明の冊封を受けたのだから、明に支配されていたと表現されるかもしれないが、琉球国王にとって、明から冊封されることは、明の官僚の立場に転落することを、まったく意味していない。
それどころか、明に貢納し中国服を着て中国語を話すことは、古琉球の相対的独立を維持する必要条件だった。
平泉政権もまた、京都政権に金や北方産物を貢納して陸奥・出羽押領使や鎮守府将軍に任じられ、京都の先端文化を取り入れたが、鎌倉政権によって滅ぼされるまで、独自の権力を保ち続けた。
かつての国家は、はるかに変幻自在で弾力性を持っていた。
いうまでもなく、平泉政権以前の北東北や蝦夷ヶ島や古琉球は「日本」の版図とは言えないのだが、現在の国家は、琉球の歴史も「日本」の歴史の一部だと強弁する。
今の「日本」国家が語ろうとする「日本歴史」は、大和・京都政権の物語でしかなく、日本列島に生起した歴史ではない。
歴史の勉強が、大和・京都政権に支配されるものとしてのアイデンティティを刷り込むのを目的としているならば、有害無益なので、学ばないほうがよい。
列島に生きる民に必要なのは日本列島の歴史であって、「日本史」などという怪しい物語ではない。

入院中は(現在もほぼ似た状況だが)、読書がはかどった。
読書ノートに、『沖縄 平和の礎』と 『この国は原発事故から何を学んだのか』と 『原発再稼働の深い闇』と 『騙されたあなたにも責任がある』と 『喜屋武マリーの青春』と 『沖縄の旅・アブラチガマと轟の壕』と 『縄文時代の商人たち』と 『日本の自然保護』と 『遺伝子改造社会 あなたはどうする』と 『大峰縁起』と 『歴史と出会う』を追加。
当分、職場復帰できる状態でなく、農作業もできないので、長年の懸案だった、チェリー=ガラードの『世界最悪の旅』を読み始めた。
990ページもの大冊だが、これだけ時間があれば、読みきれそうだ。
 |
今日は朝から谷川連峰へ業務登山の予定だった。
業務命令だからどうしようもないのだが、幕営中に暴風雨に遭遇するのは確実なので気が進まないでいたら、昨夜遅くに中止の連絡が入った。
雨の降り出しは午後をかなり回ってからだったが、終日在宅して、ホームページの手入れなどをして過ごした。
『ぼくの戦後 回想の秩父』と『両神山風土記』の読書ノートを追加。
『ぼくの戦後 回想の秩父』には、戦後すぐの時期の秩父市中心部の様子が描かれている。
ここにも、今宮神社の大ケヤキの思い出が記されており、神木が地域の精神世界と不可分の存在だったことがわかる。
日が落ちてから、風雨ともに強まってきた。
これから不安な夜を迎える。
写真は、昨日見たダイダイガサ。
最近のコメント