
寄居町・むくげの会主催の史跡めぐりに参加。
主として、旧・西ノ入村を案内していただいた。
西ノ入村をていねいに歩いたのは初めてだった。
写真は、新井周三郎が幼少期に手習いを学んだという明善寺から見た、新緑の里山。
植生は変わっているかもしれないけど、新井周三郎は、こんな景色を見て育ったのだろう。
帰秩後、畑で小苗たちに潅水。

寄居町・むくげの会主催の史跡めぐりに参加。
主として、旧・西ノ入村を案内していただいた。
西ノ入村をていねいに歩いたのは初めてだった。
写真は、新井周三郎が幼少期に手習いを学んだという明善寺から見た、新緑の里山。
植生は変わっているかもしれないけど、新井周三郎は、こんな景色を見て育ったのだろう。
帰秩後、畑で小苗たちに潅水。

明治17年10月31日の夜0時ごろ、陸軍の測量師・吉田耕作が、秩父郡矢納村の城峯神社で眠りについていたところ、同神社の小使いが狼狽して駆け込んできた。
続いて覆面の者ら数名が日本刀や火縄銃で武装のまま寝所に乱入し、耕作に向かって、「自分たちは自由党員である。今夜は、先生をご招待するためやってきた」と述べた。
「なぜ自分を招待するのか、理由を言え」と返答すると、その者は「自分は先生を下吉田村まで案内せよという命令を受けただけなので、ともかく来てもらいたい。断るならばただではおかない」と、武器を突きつけて脅迫するので、神官及び測量作業員ともども神社を出立したのは、午前3時だった。
一行はその後、城峰の山腹を下り、矢納村の間道を通って古峠に出たという。
耕作によれば古峠とは、矢納村と上日野沢村の境というから、今の奈良尾峠か石間峠のどちらかである可能性が高い。
峠についたころにようやく周囲が明けてきたというから、朝の6時前くらいだ。
作業員は無関係と思われたので、二人の作業員のうち、伊藤を解放させ、しばらく行くと門平に着いた。
奈良尾峠を越えると奈良尾耕地に行ってしまうので、古峠は石間峠のことのように思われる。
いったん解放された伊藤だが、古峠手前で再び拘束されてしまった。
20名ほどの暴徒に護衛されて、阿熊村の新井駒吉宅に着くと、5.60名ほどが列をなしており、座敷に通されると幹部が評議中で、机上には書類がおかれていた。
年配の幹部らしき暴徒から、「昨晩は大勢でご無礼申し上げ、申し訳なかった。今、人民が地方税や負債のために苦しんでおり、干戈に訴えるべきでないと説得してきたが、結果的にこのような暴動を起こさざるを得なくなった。信州・甲州にも伝令を送ってあり、味方もおいおい増えるだろう。まずは秩父郡一円を平均し、援軍の来着を待って埼玉県と戦い、コトなる日には純然たる立憲政体を樹立しようと考えているので、自分たちに助力してほしい」というようなことを、太閤秀吉を譬えにひいたり、西郷隆盛の事績を語ったり、国民のために一命を投げうつのが報国の義だなどと言って説得されたが、きっぱり断ったと、耕作は述べている。
その後、秩父困民党は下吉田村で警官隊と白兵戦を戦い、困民党・警官隊双方に死傷者が出る。
幹部暴徒から、「状況が変わったので、お引き取りいただいてけっこう」と言われたので、作業員とともに城峯神社へ戻った、と耕作は復命している。
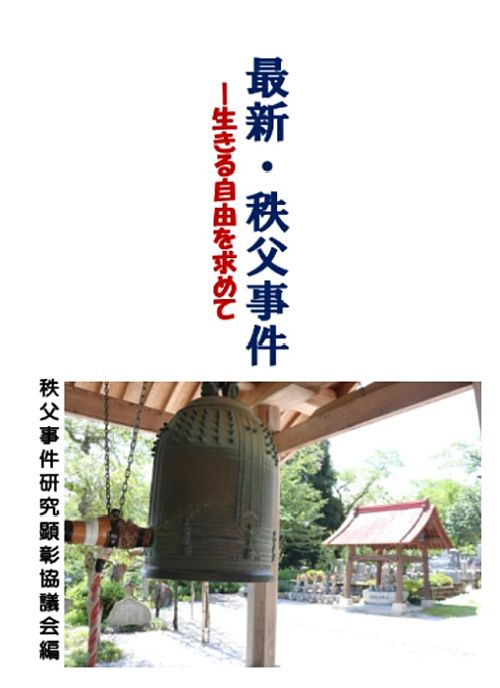
共著。最新刊。
11月10日に秩父市内で行われる秩父事件140周年シンポジウムで、パネラーやります。

小海町の文化祭が始まったということで、出かけてきた。
町の各種文化団体参加者が作った作品にじっくり見入ってきた。
こういう催しはとても楽しい。
友好団体の小海町史談会による秩父事件関係の展示もとても充実していて、見ごたえがあった。
見るだけでなく、じっくりメモを取って勉強させていただいた。
その後、秩父事件の11月9日早朝、陸軍高崎鎮台の吉野大尉と江口少尉に率いられた一個中隊が秩父困民軍に、側方から銃撃を加えた。
正面からと側方からの銃撃によって、13名が倒れ、死屍累々の惨状となった。
側方からの攻撃を担当した吉野・江口軍の陣地跡に建てられた石碑を見た。

東松山市で秩父事件シンポジウムが行われたので、参加してきた。
とても多くの参加者で、盛況だった。
写真は、カラマツベニハナイグチ。
ハナイグチを期待したが、ほとんど出ていなかった。

今年のいちごを片づけ。
いちご跡地には白菜を植える。
雨はよく降ってるのに、畑は乾く。
芽の出たネギ類などに潅水。
神社関係の用足し。
竜興寺にお参りしてから、東馬流の古戦場を訪れた。
ここには何度来たかわからない。
古戦場碑はきれいに磨いてあった。
ここで倒れた困民軍兵士のうち七名は、未だ氏名不詳。
なんとか名前がわかればいいのだが、すでに140年が過ぎようとしている。

メイン大豆の赤大豆だが、今年は最初にまいた種が干天のため発芽せず、次にまいた種もやはり、干天のため発芽しなかった。
大豆の種まき時期は6月下旬から7月上旬なので、ここまで来たらもう無理だと思われるのだが、来年の種くらいはとれるかもしれないので、この先数日の夕立に期待して、まき直し。
午後から期待通り、スコールが来た。
明治10年代に、北相木村の村の戸長・井出為吉らは大龍寺で学習会を開いていたという。
学習会のテーマやテキストが何だったのか、どのような運営がなされていたのかなどは伝わっていないが、為吉宅に伝わるフランス革命史や法律書を見れば、彼らの関心がどこにあったかがうかがえる。
明治初年は、知識に餓えた若者たちが集団で学ぶ時代だった。
一つの典型が、五日市学芸講談会だった。
すっかり晴れて、高台に建つ大龍寺の山門からは、御座山の勇姿が望まれた。
為吉たちはいつもこの景色を見ていたのだなぁと思いつつ石段を下ったのだった。

朝から鎮守の草刈り。
最高気温が出る午後(37度まで行った)は身体を休めて自宅で書き物。
もっともエアコンがないので、自宅が快適なわけでもない。
夕方から畑に出かけた。
北相木村は南相木村の隣村で、永禄8(1565)年に相木村が南北に分かれたときに成立した。
この村の自由党員、菊池貫平と井出為吉は、明治17年10月末、秩父郡三沢村の萩原勘次郎に招かれ、国会開設運動に参加するつもりで秩父困民党に飛び込んだ。
秩父に来てみたら負債問題解決のための運動だと聞かされ、一旦は「それじゃ帰る」と言ったが思い直し、武装蜂起の当日には、貫平が参謀長、為吉が軍用金集め方という困民軍の最高幹部に就いた。
為吉は富豪から軍用金を集めた際、領収書に「革命本部 印」と署名し、貫平は、困民軍本陣が総崩れになったあと、残存勢力を率いて群馬県から長野県へと転戦し、東馬流で壊滅するまで戦った。
1984年10月28日に、貫平宅にほど近い、北相木村の諏訪神社に「自由民権の雄叫び」と題された立派な石碑が建立された。
おぼろげな記憶だが、自分も、この碑の除幕式のすみっこで、話を聞いていた。
数年前まで内閣官房長官を務められていた井出一太郎代議士が、静かに参列しておられたことが印象的だった。
碑文には明治17年の村戸数250戸で秩父事件参加者約200人とある。
現在の村総人口は700人を切っているが、広いレタス畑は、よく手入れされていた。

南相木村ができたのは1565年。
佐久地方が武田信玄の支配下に入ったころだから、450年ほどの歴史がある。
江戸時代以前から存在している日本の自治体は少ないのではないか。
明治・昭和・平成の町村合併でも独立を維持し続けた。
補助金が欲しくてドタバタ合併して歴史と由緒ある自治体名を投げ捨てた日本中の市町村は、ここの爪の 煎じて飲めといいたいが、もう遅い。
南相木村から小海駅へ向かう村境は、出征兵士を送った場所だという。台座の銘文を読む。
過ぎし戦いの日 ここ別れの松の下で 征途につく若者たちが 万感を胸にいだいて 愛する家族や村人に別れを告げ その多くが帰らぬ人となった。
戦後すでに四十年 往時を偲び この尊い犠牲を決して無にしてはならないと 平和への悲願をこめ 村民相はかって ここに「不戦の像」を建てる。
昭和六十年九月二十三日 南相木村
秩父困民軍は南相木村を通っていないのだが、戸数の大多数にあたる200名ほどが参加している。

両神村の大名山へ。
黒海土耕地の延命寺から登る。道なし。
アメダスで最高値35.5度だが、とんでもない暑さだった。
明治17年の9月2日、下小鹿野村の小菅萬吉は黒海土の寺に呼び出された。
そこには田代栄助・坂本宗作・恩田宇市らが居合わせ、萬吉は、借財を年賦にする件について栄助から聞かされたという。
この会議については、彼以外に供述している人がなく、そこで話し合われたとされる内容についても検討が必要だが、黒海土の寺といえば延命寺しかない。
写真は、草深い今日の延命寺。
最近のコメント