
終日、鎮守の祭礼。
そこそこ疲れた。
祭礼幟旗の意味をあまり真剣に考えたことはない。

終日、鎮守の祭礼。
そこそこ疲れた。
祭礼幟旗の意味をあまり真剣に考えたことはない。

雪はけっこう降ったが、降り始めがみぞれだったので、積雪はすぐ溶けた。
確定申告の書類を作ったので、税務署に持っていったのだが、「予約してありますか ?」と言われた。
予約しないと書類のチェックはしてもらえないらしい。
若い署員の方が、おれの携えていた書類をチラ見して、「これじゃどっちにしたってダメでしょ」とつぶやいた。
税務署とLINEで友だちになったら予約できます、と言われたのだが、悪いけどおれは、税務署と友だちになりたいとは思わんのだよ。
でも、友だちになってねと言われてヤダヨというほど、心が狭いつもりはないので、税務署の人にスマホを渡して、税務署と友だちになった。
畑で草むしり少々。

とても珍しいものだそうなので。
軽トラのタイヤ交換。
しくじって、ホイールナットとボルトの山を潰してしまった。
最初にレンチを蹴ったのがいけなかったのかも。
大豆摘みの続き。
トンネルのサニーレタスなどに潅水。
晴天続きにもほどがあるというほど、晴れの日が続いてチト困っている。
内田樹という人が日本列島をどう守るか 過疎化に"100万人の引きこもり"が役立つワケという文章を書いている。
この中で内田樹氏は、100万人の「引きこもり」に山里へ引きこもってもらうことで、地域を守ることができると述べている。「部屋にこもって1日中ゲームやっていても、ネットをしていても」いいそうだ。
「気が向いたら、畑を耕して野菜だって作れる」らしい。
引きこもることしかできない彼らでも里山の「歩哨」たりえるのだという言説のバックボーンにはまず、引きこもっている人々を「現状、社会の役に立っていない」と見下す意識がある。
内田氏は、共同体を維持するための、祭りを始めとする各種地域活動や、獣害防止のためのハンターの活動や、厳重な防獣バリケードを築いて畑仕事をする労苦など、何も知っていない。
「気が向いたら、畑」。人をこれほど絶望させる言葉に出会ったのは、久しぶりだ。

集落の祭礼。
疫病よけの神さまなので、タイムリー。
今日は一日、仕事休み。
自宅まわりに鹿わなをかけてもらった。
写真は船形山のブナ林。

ピーマン小苗の植えつけ。
カボチャ植えつけの準備。
アスパラガスの植え替え。
草むしり。
ほぼこれだけで一日が過ぎた。
写真は、三ツ山から望む太田部・楢尾耕地。
今も耕されている畑が見える。

軽トラの車検。
暮らしのためにはどうしても必要な道具なのだが、収入が少なくなったので、こういう支出はけっこう痛い。
芽の出た菜っ葉に潅水。
小松菜とほうれん草は発芽したが、人参は出ない。
白菜の片づけ。
じゃがいも予定地とネギ予定地の耕耘。
ウドのうねに落ち葉掛け。
この冬は心が弱くて、落ち葉堆肥を作らなかった。
小倉山登山口の座禅草はちょうど見ごろだった。

大雨になると、家のわきを流れている小渓流がもの凄い音を立てる。
水流がドウドウと鳴ってる間は、まだましで、激しい雨になるとドウドウ・ゴロンゴロンという音に変わる。
大きな石や流木がのべつ幕なしに流下する恐ろしさったら、ない。
昨日はそれがほぼ一日中、続いた。
国道沿いでは至るところで、土砂と倒木が歩道に押し出している。
畑では、先の17号で半壊したゴーヤが全壊し、四角豆が半壊し、その他の多くの作物が倒伏した。
とはいえ、去年ほど絶望的な状態でもないので、まあ、よかった部類。
昨夜から、かなり強い風が吹いている。たぶん風速にして5ないし15メートルほど。
ヤフー天気の風情報だとほぼ無風になってるので、この情報は正確ではない。
恐ろしい一日だった。
明け方から、かつて経験したことのないような豪雨が、ほぼ終日、降り続いた。
もちろん家から一歩も出ることができなかった。
屋根の樋にゴミが詰まると雨水が樋から溢れてそこら中に降り注ぎ、崖上に立っている自宅の斜面を液状化させる。
昨日、屋根に登って樋掃除したのだが、今日また樋が詰まった。
土砂降りの雨の中、屋根になんか登れないので、二階の窓から棒を使って樋掃除した。
雨が強かったのがむしろ幸いして、樋のゴミを流すことができた。
が、一部の樋は手も出せなかった。
夕方から強風が吹くはずだったので、雨戸をすべて閉めた。
めったに閉めないので、雨戸の桟にゴミが詰まっていたが、とりあえず雨戸が動く程度に掃除した。
雨の強いときにはYahooの雨雲レーダーで一時間あたり40ミリから80ミリの間を行ったり来たりしていた。
心配しても仕方がないのだが、かといって仕事や勉強をする気にはとてもなれず、一日中、不安を抱えてぼんやりしていた。
暗くなるころから、ときおり強い風が吹きつけたが、風に関しては、今のところさほどひどくはなかった。
台風の中心は現在、至近距離にいるはずだが、雨が降ってはいるものの、ピークは越えたような気がする。
これから心配なのは、関東平野のあちこちである。
荒川の場合、熊谷あたりの水位は、やや下がりつつある。
このまま行けば大災害は回避できそうだ。
しかし、二瀬ダムが22時から「異常洪水時防災操作に移行します」と告知している。
予断はまだ、許されない。
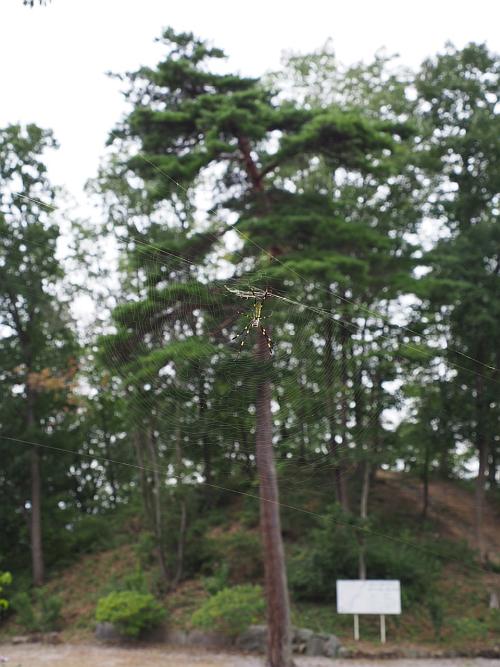
稲穂山古墳でコナラの間伐を手伝ったのは6年前だった。
その時のエントリで「秩父地方の古墳は群集墳として築かれたものだというのが一般的な理解だから、稲穂山古墳は、一般的な秩父の古墳とは性格が異なると思われる」「秩父地方の群集墳の多くは、墳丘の下部に緑泥片岩で横穴式石室を構えているのだが、稲穂山古墳は墳丘の頂部に竪穴式の石室らしきものがある」と書いたのだが、その後、稲穂山古墳に関する研究に接する機会がなかった。
ムクゲ公園で稲穂山古墳に関する講演会があると聞いたので、でかけてきた。
講演は、宮瀧交二氏の「和銅遺跡と埼玉の渡来文化」と大谷徹氏の「稲穂山古墳の謎を探る」で、いずれも興味深いものだった。
大谷氏が紹介された現在の研究によると、立地や石室の形態など、稲穂山の形態が秩父地方の他の古墳と異なっているのは、築造された年代が異なっているからで、5世紀半ばから6世紀前半に築造されたというのが現在の説らしい。
稲穂山古墳の眼下には、飯塚・招木古墳群、大塚古墳(群)、上長瀞・金崎古墳群など、7世紀後半以降に築造された群集墳があるのだが、定説に従えば、稲穂山古墳の築造当時にこれらの群集墳は存在せず、いわば秩父地方で唯一の古墳だったことになる。
しかも時代的には、北武蔵の王者の墓だった埼玉古墳群とほぼ重なることにもなる。
埼玉古墳群は、平野に盛土して築かれた大型の前方後円墳であり、竪穴式石室を持ち、稲穂山とは規模も形も全く異なる。
武蔵国造に比定されるだけあって、被葬者の権力の巨大さは、十分理解できる。
稲穂山と埼玉古墳群が同時代だったとすれば、その規模からして、秩父の有力者は埼玉古墳群の被葬者たちに従属的な立場にあったと考えざるを得ない。
古墳の築造時期をその形態から推定する方法が、すべてのケースにおいて妥当かどうかはわからないから、稲穂山が5世紀半ばから6世紀前半に築造されたという説の説得性は十分だと思えない。
稲穂山と秩父の他の古墳との形態的相違を、築造時期の相違から説明するのでなく、被葬者の階層の相違という形で説明する視角はありえないだろうか。
稲穂山古墳は、荒川の河岸段丘上に築かれた群集墳と、その周囲に展開していたであろう集落を見下ろす位置にある。
決して楽ではなかっただろうが、古代の秩父の民の暮らしは、とりあえず平穏に営まれていただろう。
秩父盆地という小天地の支配者は、民の暮らしの風景を眺めて満足していただろう。
かの小天地の支配者が葬られるのに、稲穂山がもっともふさわしい場所だったと考えるのが、ストーリーとしてはロマンティックなのだが。
この古墳の築造時期を明確に示す何らかの発見がなされることを期待したい。
最近のコメント